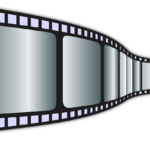僕がまだ小学生の頃、祖父に天体望遠鏡を買ってもらいました。 祖父は元・憲兵だったためかやたらと教育については熱い思いのある人でした。
この他にも当時はまだ高価だったパソコンや、弟には顕微鏡など、とにかく物質的な援助は惜しまなかった人でした。
でも僕はおばあちゃん子でしたけどね。(笑) それはともかく、今回は天体観測の思い出の話です。
僕は小学校3、4年生くらいの頃から天体に興味を持ち始め、ちょうどその頃テレビで放送されていたカールセーガン博士の「コスモス」のドキュメンタリー番組なんかをかじりつくように観ていました。
多分祖父は、そうした僕の行動を見ていたんでしょう。 ある日、天体望遠鏡を買ってくれたんです。 確かビクセンの屈折望遠鏡だったのを覚えています。
天体望遠鏡を持っている人であれば共感されると思いますが、最初に攻略する天体はまず、「月」だと思います。
地球上ではまず太陽と並んで最も目立つ星ですし、太陽を見るのと違って危険性がありません。
一番倍率の低いレンズを取り付け、初めて望遠鏡の視界に月を捉えたとき、本当に感動しました。
もちろん、テレビや図鑑では月なんか何回も見ています。 でも自分の望遠鏡で、自分で視界にとらえ、自分でピントを合わせた月は全然格別でした。 ちょうどキャンプで自分たちで作ったカレーが美味しいと感じるメカニズムとまったく同じですね。
でもそんな感動的な月も毎日見ているとさすがに飽きてきます。 そろそろ他の星にも食指が動き始めます。
ただ地球上からですと、普通の望遠鏡ではいくら倍率の高いレンズをつけても天上のほとんどの星は「点」のままです。
なぜならそれらは太陽系の外にあるからです。 あまりに遠いところに存在しているため、いくら倍率を上げても点のままなんですね。
ですので自然、ターゲットは「惑星」になってきます。 惑星は他の星に比べて明るいため、探すのは難しくありません。
「明けの明星」、「宵の明星」という呼び方をされる金星なんかも、語感そのままの明るさを誇っています。
僕は惑星の中でも大斑点が特徴的な木星と、なんといっても輪が特徴的な土星を狙うことにしました。
片っ端から、それらしい明るい星にピントを合わせていきます。 初めのうちはただの明るい点が続くだけでしたが、7~8回目、ついにとらえました!
「本当にあったんだ。」それまでテレビでしか見たことがないものを、今実際に目の前で見ている。 土星の輪のことです。
この感動をこの天体は存在するだけで何人の少年たちに与えてきたのでしょうか? 僕も見事にその一人に加わりました。
家族まで呼んで大騒ぎしましたね。 僕一人の大事件でした。 土星はしばらく夢中になりました。
その後、木星も無事に発見できましたが、なぜか土星ほどの感動はありませんでした。 これは単に順番の問題だったのでしょう。
一応この後も他の惑星に挑戦しましたが、星自体にあまり魅力がなかったり、探す難易度が高かったりで断念しました。
僕としても土星、木星でもう十分お腹いっぱいでしたしね。 僕のつかの間の天体生活は2年ほどで終わりました。