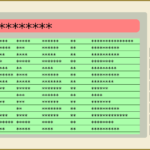僕は一時期、自己啓発書や格言集にハマった時期があり、大学の図書館で借りたり、古本屋で立ち読みしたり、書店で購入して読んだりしていました。
今思い返してみますと、数ある様々な文学(?)の中でも何故とりわけそんな分野にはまり込んでいたのか不思議な部分もあります。
ただ冷静に考えてみますと、僕は昔から人間の心理や精神状態というものに興味が深い方でした。 つまりこういう心理状態になると人間はこういった状況に陥り易い、こういった行動を取りやすいというような研究みたいなものを好んだわけです。
最初に述べた「啓発書」や「格言集」というものはまさにそうした人間の心理を短く無駄なく、時に一生頭から離れないような美しい文章で核心を突くために、僕は好んで読みふけったのでしょう。
中国の古典の「論語」、「老子」、「荘子」、「孫子」、「韓非子」などは当時なかなか熱中して読みふけったものでしたが、今振り返ってみると「孫子」以外はどうも実用性に乏しいというか、精神論としては理解は出来ても、これらを実際に実生活に適用してしまうと人間関係に破綻が生じたり、日々の生活の糧を得ることが困難になってしまいます。
例えば「韓非子」のような非情なまでの法治主義に徹してしまうと、人は思いやりや優しさといった人間らしい感情を持つ余地をなくしてしまい、人心は荒廃してしまうでしょう。
一方で「老子」や「荘子」のような身の回りで起こる全ての外的要因をあるがままに受け入れ、流れに逆らわずに身を任せて生きる、というのではニートの言い訳と何も変わりません。
三国志好きなら誰もが知る蜀の名宰相、諸葛孔明は軍師として有名ですが、実は戦よりも内政の方を得意としていたようです。
「彼は国中の人民から恐れられていたが、彼を恨むものはただの一人もいなかった。」ということは彼の信賞必罰は徹底していたものの、その公平性も半端なものではなかったということなのではないでしょうか。
「泣いて馬謖を斬る」という彼のあまりにも有名なエピソードは、このことを如実に証明していると思います。
諸葛孔明は非常に書物を好んだらしいので、恐らく僕が上に挙げたような古典にも精通していたでしょうが、彼はそのどれかの思想に極端に傾倒することなく、彼の素晴らしい人間性でそれぞれの良いところを取り入れたのでしょう。
他にも僕が今でも読んで記憶に残っている格言集は谷沢永一さんの「人間通」、ラ・ロシュフーコー箴言集などですが、これらはまた機会を改めて書きたいと思います。
内容のあるいい本を読むことは、物の見方を増やしてくれるという点で有益なものであることは確かですね。